- ホーム
- 患者会/患者支援団体の活動紹介
-
世代を超えて受け継がれる「東北ヘモフィリア友の会」
過去から現在、未来へとつなぐ患者会の意義と活動への想いについて、黎明期を知る代表と、これからの患者会のキーマンとなりつつある20代および40代のお二人にお話をうかがいました。
(2024年8月31日、TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口にてインタビュー実施)
目次
たゆみなく続けられてきた診療の充実への働きかけ
- 東北ヘモフィリア友の会(東北友の会)について教えてください。
-
藤野秀一さん:東北友の会は、1968年に患者間の交流・情報交換、就学・就職時の支援、血液製剤への公費助成の推進などを目的として、当時、東北6県で唯一、血友病の診断ができた東北大学病院内に第三内科の森先生が中心となり設立されました。
現在、年1回の総会とその後の医療研修会のほか、「母親の会」やSNSグループでの集まりなどがあります。宮城県を中心に、患者会のない福島県、山形県、秋田県を含めた近隣の患者さんとその家族も参加されています。 - 医療機関とは、どのように連携しているのでしょうか。
-
藤野秀一さん:東北大学病院・仙台医療センター・宮城県立こども病院とは、医療研修会の講師やさまざまな相談のさいにご協力いただいています。
また、宮城県立こども病院とは、同院設立の話が出た2000年ごろから関わってきました。当時の東北大学病院の小児科の堺先生(後にこども病院の副院長)が、血友病もここで診るようにしたらどうかと提案され、私たち東北友の会も病院開設の署名活動などに取り組みました。開院後は保因者でリスクのある方はこの病院で出産したり、新生児から診てもらったりということができています。この地域で専門医が少ないなか、血友病の診療を続けてもらえる心強い小児専門病院です。また年に1度、7月の最終土曜日に、こども病院で開催される血友病の勉強会でお話しさせてもらうなどして、東北の患者さんやご家族のための支援活動を続けています。 - どのような方が参加されていますか。
-
藤野秀一さん:名簿上の会員は70家族で、50代以上は長く参加されている方が多く20名以上、子どもとその親御さんが20家族くらいで、残りは中間層の世代になります。
また10家族以上が福島、山形、秋田の他県の方々で、宮城県内の病院で血友病の確定診断を受けたときに、東北友の会を知って入会される方も多いです。
時代・世代を超えて困りごとを相談できる存在であり続ける
- 東北友の会に関わられたきっかけは何でしょうか。
-
藤野秀一さん:東北友の会に入ったのは14歳のときでした。ちょうど全国で友の会の活動が始まったころです。血友病で入院したさいの担当医師が、東北友の会を立ち上げた東北大学病院の森先生と知り合いだったことがきっかけで、親とともに入会しました。
60年近く前、私が小中学校のころは血液製剤が非常に高額かつ健康保険の適用にならない時代で、医療費の負担が問題になっていました。患者は小・中学校は入学できるものの、高等学校は安全性の問題などで入学を拒否されることも少なくなく、私の少し上の先輩たちは、通信教育で高等学校を卒業されている方々が多く、入学・進学に苦労していた時代でした。こうした状況におかれた患者の親たちの努力が患者会設立の背景にありました。伊藤雄介さん:私は血友病Aの軽症患者で40代です。1年に1回ほどの通院で、怪我をしたときだけ注射するという生活でしたので、同じ血友病の弟以外の他の患者さんを知りませんでした。35歳くらいで右足首が関節症になっていることが分かり、こうした困りごとが生じたときに相談できる人を求めて、血友病の伯父が参加していた東北友の会に入会しました。自分と同じような悩みを持っている方々のお話を聞けたら、と思ったのが参加の動機です。
桜井佑輔さん:私は血友病Aの重症患者で、20代です。母が保因者、父は血友病とは無縁で、小さいときに母に連れられて東北友の会に入りました。母は長く役員を務めていましたが、私はかなり活動的なタイプで、学齢期になるとスポーツや趣味、友達との交流に忙しく、会からは足が遠のいていました。ただ怪我も多くて捻挫や打撲を繰り返していましたので、親には心配をかけたと思います。そのようななか、26歳になってすぐのことですが、これまで何も言ってこなかった父から「そろそろ患者会にいくことを考えてはどうか」と真剣に参加を促されました。「いろいろと勉強もできるし、これまでの経験が他の人の参考になるかもしれない」と背中を押され、“じゃあ、行かないといけないな”と、本当に久しぶりに総会に出席しました。
未来へとつなぐ若い世代の想いとエネルギー
- 東北友の会に参加して得られたもの、心の変化などはありましたか。
-
桜井佑輔さん:久々の総会でさまざまな患者さんと出会いました。今まで自分のやってきたスポーツや趣味のことなどをお話しすると、「そんなこともできるのか」と驚かれることもありました。会への参加は、自身の勉強になるのはもちろん、私にもできること、伝えられることがあるんだと気づきにつながりました。そうして、私自身も他県など、いろいろなところへ行って、より多くの患者さんたちと触れ合ってみたいとの想いがますます強くなりました。
伊藤雄介さん:私自身は大人になって、困ったことが生じてから東北友の会に入り、同年代や先輩方の話を聞いて救われたことが数多くありました。進学や部活、就職、結婚といったライフステージによって悩みや困りごとが異なってくる病気なので。私が全国のイベントに参加しているのも、自分自身がイベントに参加したいというのもありますが、そこで聞いたさまざまな方の話を自分の経験も含めて、東北友の会の皆さんにお伝えしたいと思うようになったからです。
- 若い世代の患者さんとはどのように関わっていますか。
-
桜井佑輔さん:現状、総会などで同年代の方に会うことは少ないのですが、私の話が子どもの親御さんなどには、結構響くことがあるようです。例えば、私は学生時代にサッカーと剣道、そして格闘技をしていました。格闘技は対戦相手と闘うのではなく、エクササイズが目的でしたが、足首や膝などを痛めながらも続けていました。そうした経験が新鮮に感じられるようです。
藤野秀一さん:親御さんは、子どもが血友病と分かると、藁にもすがる思いで1~2年間は参加してくださるのですが、自己注射や管理ができるようになってくると足が遠のく方が多いのが現状で、若い方の参加も少ないです。これは治療が発展し、医療費も公費負担になり、昔に比べると困ることが少ないからだと思います。
桜井佑輔さん:たしかに、困りごとは減ってきたと思います。しかし、患者会に参加することで、運動後のケアなどまだまだ患者同士で学べることがあるのも事実です。私自身、怪我をしやすい部位に対して十分なメディカルケアができていれば、今も多少残っている関節の障害などを防ぐことができたかもしれないと思っています。自分自身の経験からできたこと、逆に対策が足らなかったことを客観的に分析して、若い方や親御さん方に伝えられたらと思っています。
- 「母親の会」では、どのような活動をされていますか。
-
藤野秀一さん:お母さんたちのコミュニケーションの場「母親の会」は、‘何でも話そう‘という趣旨で開催されています。PTAの集まりでは話せないような病気の日常のこと、困ったことを、また総会などとはちがって肩に力を入れないで話せる場となっています。そうしたお母さん同士の中から、イベントがしたいという要望が出れば、協力しています。
- 患者会を若い世代へとつなげるため、どのような活動を考えていますか。
-
藤野秀一さん:現在、改めて若い人たち向けのイベントができればと考えているところです。私が20代のころにはサマーキャンプをしたり、温泉旅館で自己注射の勉強会をしたりしていました。イベントなどを通して、同じ悩みを持つ方とのつながりを作ってもらえればと考えています。
伊藤雄介さん:私自身、キャンプが好きなのでサマーキャンプは候補の筆頭と考えています。また宮城県の秋の恒例イベントである芋煮会などもフランクな集まりにして、県外の患者会の方もお呼びできたら、地域同士のつながりもでき、面白いのではないかと思っています。
桜井佑輔さん:勉強の機会をいただいて、東京や大阪など東北以外でも活動するなかで、大阪のYHC(Youth Hemophilia Club)という若い世代の会にも参加するようになりました。そのさまざまな活動を学び吸収して、いつか仙台市で、勉強会や交流会などを含めた大規模なイベントをやりたいと思っています。
ゆるやかなコミュニケーションの創出で、活性化を目指す
- 東北友の会からの情報発信や相互連絡はどのようにされていますか。
-
藤野秀一さん:時代の流れもありますし、さまざまな紙の資料をその都度郵送できるわけではありませんから、インターネットを使った情報発信ができるよう、HP、メール、SNSグループ等を整備しました。SNSなどは、総会以外の新たなコミュニケーションの機会を創出することができ、日程が合わずに総会に出られないという人たちに、ぜひ活用していただきたいと思っています。また相談窓口としての機能も考えています。YHC等で活動をしている桜井君には、広く若い方々からのアクセスがあった場合に対応してもらえると思います。
桜井佑輔さん:私も伊藤さんもSNSグループに入っていますが、お互いのことを知るために食事会の企画をするようになりました。直近の食事会には6名ほどが集まる予定です。身近なところでも交流を深めていきたいですね。
藤野秀一さん:桜井君が話した食事会は、当初は若者の集まりのつもりでしたが、「母親の会」にも声をかけて一緒に交流できればと考えているところです。
- 最後に、伝えたい想いやメッセージがあればお願いします。
-
桜井佑輔さん:活動を続けるなかで、これまでの歴史についても若い世代の皆さんに知っていただきたいという気持ちが大きくなりました。私自身も代表がお話しされた医療費の自己負担の問題が、意外に近い過去の話であったことにショックを受けました。
これまで当たり前と思ってきたことは当たり前ではなく、過去から積み上げてきた歴史の成果であることに対する認識や感謝はとても大切だと思っています。伊藤雄介さん:困らないで生活できていると、積極的に参加しようとはならないでしょうけれど、こういう患者会の歴史を知って、何かあったときに頼れるのはもちろん、こういった取り組みの流れに加わりたいという人がいてくれると嬉しいと思います。
藤野秀一さん:伊藤君、桜井君たち若い方とともに、次の世代につなげる、吸引力のある患者会を目指して検討を続けていきたいと思っています。
小さな困りごとでも、世代ごとの悩みでも、何か知りたいことがありましたら、お気軽にご連絡ください。
お話をうかがった方
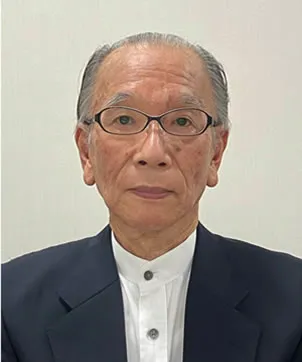
代表 藤野秀一さん
血友病A(70代)。東北ヘモフィリア友の会発足当初に14歳で入会。会の歴史とともに歩み、2006年に代表に就任。若い世代をキーマンとして参加・活動を後押ししている。

伊藤雄介さん
血友病A軽症(40代)。30代で血友病性関節症を発症したことがきっかけで入会。その後コミュニティ活性化のために全国会でのイベント等に参加し、情報をフィードバックしている。
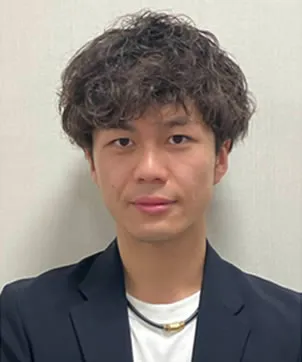
桜井佑輔さん
血友病A重症(20代)。スポーツなどに打ち込んだ学齢期を経て20代で患者会に再参加し、今は全国会のイベント等に積極的に参加している。若い世代でつながるYHC(Youth Hemophilia Club:ユース・ヘモフィリア・クラブ)のメンバー。
東北ヘモフィリア友の会
- 【創 立】
- 1968年1月
- 【代 表】
- 藤野秀一
- 【会員数】
- 70家族
- 【所在地】
- 宮城県多賀城市山王字北寿福寺1-68
- 【連絡先】
-
TEL:022-368-8427
Mob:090-8789-2138
Mail:sannofuji@yahoo.co.jp - 【活動内容】
- 宮城県及び近隣の福島県、山形県、秋田県(3県とも患者会不在)を含めた患者とその家族で構成されています。
現在、年1回の総会・医療研修会のほか、血友病の子どもの母親で構成される「母親の会」やSNSグループでの会合を実施、セミナーの案内や冊子の配布(不定期)なども行っています。また、宮城県内の医療機関と連携し、支援や協力の関係を続けています。
